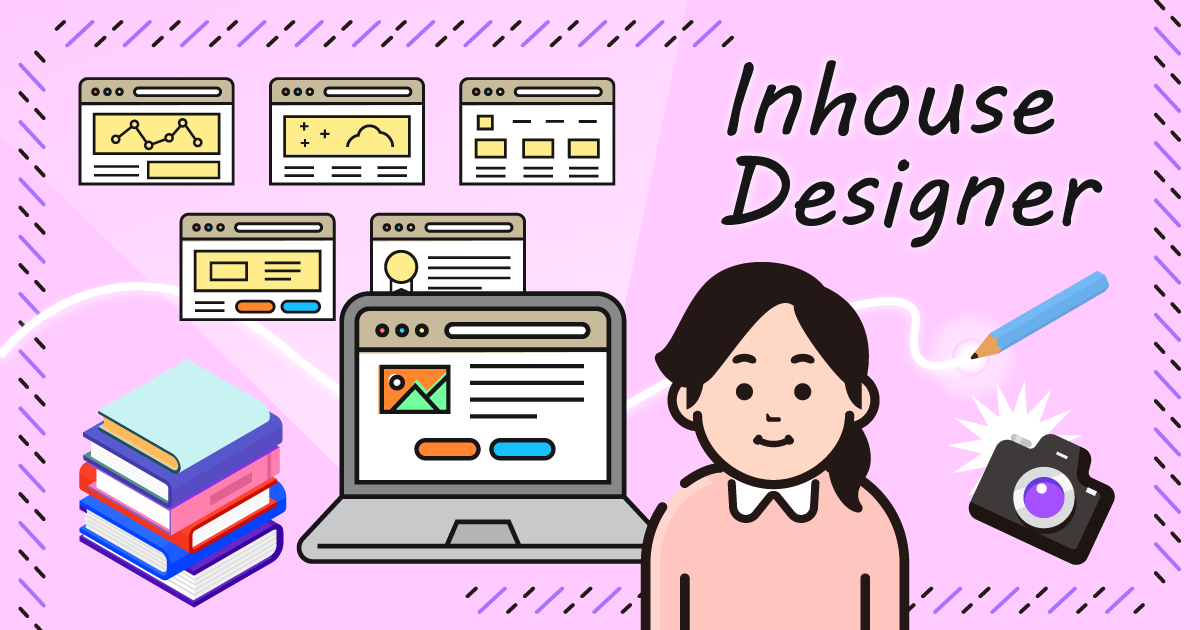インハウスデザイナーという言葉を聞いたことがありますか? 社内デザイナーや企業内デザイナーとも呼ばれています。本記事では、インハウスデザイナーとはどのような職業なのか、インハウスデザイナーのメリットやデメリット、どういったステップアップができるのかについて、地方のメーカーで15年以上インハウスデザイナーを務めた経験のあるピナトンが、実態を紹介します。
インハウスデザイナーとは?
デザイナーと言えば一般的に、デザイン事務所や制作会社に所属し、他社が外注したデザイン業務を受託する商売をイメージされる方が多いかもしれません。インハウスデザイナーは、そうではなく、自分が所属する会社、つまり自社のためにデザインを内作する職種です。
デザイン事務所などの場合は、周囲は皆デザイナーかもしれませんが、インハウスデザイナーの場合、社内で同じ職種の方はかなり少人数だったり、場合によっては1人だけというケースもあります。
インハウスデザイナーになる方法は?
では、インハウスデザイナーになるためには、どうすれば良いのでしょうか。
美大や芸大、専門学校などを卒業し、どんなことができるか、どんな実力があるのかを示すポートフォリオを作成して、インハウスデザイナーを募集している会社に応募し、就職するケースが多いです。
一方で、ピナトンのように学生時代デザインを勉強したものの事務職として就職。その1年後、スキルを見いだされてインハウスデザイナーとして本格デビューという流れもあります。
社内でデザインの必要性が高まった結果、全く勉強したこともないし、特にデザイン分野について興味があるわけでもないのに、なし崩し的にいつの間にかそういった立場にいた、という方もいらっしゃるかもしれません。
インハウスデザイナーのお仕事範囲
メーカー勤務のピナトンは、営業広報やプロモーションコンテンツ制作のチームに所属し、下記の制作について手掛けていました。
オフライン媒体
- 製品・サービスのカタログ
- 展示会DM
- ちらし
- ポスター
- 名刺
- 新聞・雑誌の広告
オンライン媒体
- 製品・サービス紹介のEPUB
- メルマガ
- バナー
- 自社公式サイト
- 自社ブログ
- 製品・サービス紹介のLP
- 販売支援として製品・サービス紹介のプレゼン資料(パワーポイント)
このように、幅広いプロモーション素材を扱っています。勤め先によっては、上記に加えて製品パッケージや、製品自体のデザインを担当することもあるでしょう。
インハウスデザイナーがこれら全てを企画して、最終的にリリースまで責任を持つのは、かなり大変なことと思われるかもしれません。ですが、オフライン/オンライン関わらず、同じビジュアルを一貫して使用することで、ブランドイメージの統一化を図ることが多いため、すべてイチから制作するというわけではありません。工夫次第では、効率アップした上で、訴求力を高めることもできるのがインハウスデザイナーの醍醐味です。
また、自社サイトのリニューアルなど、社内のインハウスデザイナーだけで賄えない程大規模なプロジェクトの場合や、繁忙期の制作業務については、社外へ外注するケースもあります。
インハウスデザイナーに必要なスキル・知識
インハウスデザイナーの業務例を紹介しましたが、これらの制作を担当するためには、次のようなスキル・知識があれば便利です。
グラフィックデザイナー
- Adobe Photoshop(写真加工などの画像処理からバナー作成まで)
- Adobe Illustrator(イラスト作成や、ポスター/ちらし等1枚もののデザイン制作に最適)
- Adobe InDesign(カタログなどの冊子デザインからEPUB作成まで)
最近だと、CANVAなどのオンラインサービス(無料プランあり)も使いこなせていると、より作業の幅が広がりそうです。ピナトンの場合、これに合わせて3Dソフト(3ds MaxやLightWave 3Dなど)やUnityも触った経験が少しあります。
Webデザイナー
- HTML(Webサイトの骨組みを作ります)
- CSS(Webサイトの装飾を設定します)
- JavaScript(Webサイト内の特殊な動きを設定したり、アプリ化などもできます)
- PHP(問合せフォームや検索機能、ログイン機能など、Webサイト上で動くものを実装するためのプログラミング言語です)など
この他、社会人として基本的なお話にはなりますが、コミュニケーション力が重要です。
インハウスデザイナーの場合、自らがプロモーション計画を立てて、企画立案するケースもありますが、開発部門や営業部門からの依頼で、社内外向けのコンテンツを制作することもよくあります。この場合、身内である社内の方々からコンテンツのターゲットや目的、仕様や納期といった要望事項を念入りに聞き取った上で制作する必要があります。

非デザイナーの方々の「ふわっとした概念やイメージ」を可視化していくのは、時に骨が折れることもあります。ですが、自分が制作したものが依頼主に喜ばれたり、実際に売上に貢献したりすると本当に嬉しいものです。
また、外部のデザイン事務所などへ外注する際は、長くお付き合いできるパートナーとして良好な関係を築けるように留意したり、自社のブランディングを忠実に再現してもらえるよう、的確なディレクションを行うことも重要となります。
インハウスデザイナーのメリット
そろそろインハウスデザイナーの外枠が見えてきましたでしょうか。続いて、地方のメーカーで長年インハウスデザイナーを務めてきたピナトンから見た、インハウスデザイナーのメリットについて紹介していきます。
多くの種類・媒体のデザインを制作できる
デザイン事務所や制作会社の場合、企業自体がデザインに特化しているため、組織内が媒体や業界別に細分化されていて、所属するチームが専門的に任されているもののみデザインすることが多いです。例えば、医療業界向けのSNS広告チームであれば、その領域に特化した経験値を高めることができます。
一方、インハウスデザイナーは、自社を取り巻く業界における様々な媒体のデザインを担当することができます。自社製品・サービスの認知向上や集客目的のSNS広告を作りつつ、(カスタマーサクセスの分野になるかもしれませんが)購入後サポートのメルマガも作成するなど、カスタマージャーニーの全てを俯瞰した上でデザインしていくことができるため、経験値は必然的に高くなりますし、退屈することはありません。
カスタマージャーニーとは:お客様の心情や行動が、時を追ってどのように変化していくのかを可視化したもののことです。製品やサービスとの出会いから、検討や購入、その後の共有まで、一連の流れを旅に例えています。こういった変遷は、AIDMAやAISCEASなどの購買行動モデルが有名です。
あらゆる工程に関わることで完成物も手にできる
インハウスデザイナーの業務範囲は、純粋なデザイン作業だけに留まりません。ピナトンの会社では、自社製品のカタログを制作する場合、カタログのデザインデータを作成後、カタログの紙を選び、実際に印刷会社へ入稿して色校正を確認。印刷完了後は、本社、支店、現地法人など、営業の現場へカタログを発送するところまで行っていました。
自分でデザインしたものが、実際に何千部と印刷され、国内外へ発送されてお客様の手に届くことになる過程を全て目にすることができるのは、インハウスデザイナーならではのことだと思います。
実力がそこそこでも許される
特に地方の中小企業の場合、インハウスデザイナーが社内に数多く在籍していません。デザイン業務は特殊なため、誰にでもできそうで、できないものなので、見栄えが良くて売上に貢献できるデザインを連発すると、自然と社内で一目置かれる存在になっていきます。それは例え、そのデザインが、一流の広告代理店から出てくるような最先端でアーティスティックなものでなくても、です。
たくさんのデザイナーが所属するデザイン事務所などとは違って、競争相手が少なかったり、いなかったりする分、能力が一定に達した時点で認められる「ゆるさ」は、ストレスフルな現代社会においては大変おいしい要素かもしれません。
インハウスデザイナーのデメリット
メリットも豊富なインハウスデザイナーですが、やはりデメリットも存在します。
新たな知識・情報の収集はやる気次第
社内で同職種の方が少ない分、デザインに関する情報収集は担当者個人で行うことになります。例えば、Adobeのソフトの最新機能や、Google Analyticsの活用方法、広告出稿のノウハウなど、専門性の高い技術的な情報は、常にアンテナを張り巡らせていなければキャッチアップできません。もし自分が見逃してしまえば、誰も気づかないままという事態も起こりうるだけに、内容によっては責任が重大です。
最近ですと、Google AnalyticsのGA4設定など、早めにやっておかないと困り事が発生する案件(来年以降に前年同期比などの数字が出せなくなるなど)がありました。
師匠がいないことがある
インハウスデザイナーは、師匠となる先輩デザイナーが存在しないケースもあります。その場合は、デザインに関する第三者的な意見をもらったり、ディレクションを受けることができません。
「このデザインで問題ないだろうか」
「ブラッシュアップしたいけれど、何を変更すれ良いのか分からない」
「もっと効率よくデザイン業務を進めたいけれど、尋ねる相手がいない」
自分のデザインに対して他人からのフィードバックをもらうことは、大変勉強になります。インハウスデザイナーである限り、デザインの方向性は自社のブランディングに沿ったものであるべきなのに、ふとしたところで自分好みのテイストが前に出てしまって、ブランドイメージがブレてしまうことにもなりかねません。(必ずしも、ブランドイメージとデザイナー個人の好みが合致しないためです)
そういったことを防ぐためにも、一緒にデザインを検討し、忌憚ない意見を交わし合えるデザイナーの同僚や師匠の存在は大切なのですが、こういった人材に恵まれていない現場も多いようです。
社内で「声の大きい人」の意見に流されがち
社内においてインハウスデザイナーがレア職種である以上、たいていの他の社員には、デザインに関するセンスや知識を期待できません。にも関わらず、個人的な好みとインハウスデザイナーが制作したデザインを照らし合わせて、勝手な修正指示を飛ばす方もいらっしゃいます。
それが役職のついた上層部の方であれば、平社員のインハウスデザイナーは従わざるを得ないこともあります。

せっかく細かな配慮を積み重ねて設計したデザインが、一瞬でダサくなり、悲しい思いをすることもあります。
よくあるのは、ぽっかりと空いた空間に、何か新たな要素を追加する指示です。何もない空間はデザイン要素の1つであり、「抜け」があるからこそ垢抜けるデザインは数多くあるのですが、それを専門外の方へ理解してもらうのは、経験上かなりハードルが高いです。
デザイン以外の仕事を任されることがある
インハウスデザイナーは、名前の通りデザインするのが主な仕事です。しかし、デザイン専門の制作会社でもない限り、デザインに直結しない別業務が発生することもあります。
ピナトンの場合は、これまでに下記のようなことも行いました。ここまで幅広く携わるケースは少ないかもしれませんが、参考にしてください。
- カタログの在庫管理や発送
- 自社製品の撮影手配
- 展示会・イベントの準備(社員の名札やセールスマニュアルの作成、展示物の準備など)
- 予算管理
- 広告運用
- 自社サイトのアクセス解析
- 競合調査
- マーケティングオートメーション(MA)ツールの運用
- ブログの運営・記事執筆
インハウスデザイナーのステップアップ方法
インハウスデザイナーは、様々な経験を積むことのできる「業務の多様性」と、自社内のレア職種だからこその「自由」と「ゆるさ」がメリットです。その反面、デメリットもあることを紹介しました。では、どうすればインハウスデザイナーの困りごとを解消し、将来的にステップアップしていけるのか、いくつかの方法を提案していきます。
企業のブランディングへの参画
インハウスデザイナーは、主に視覚的なブランディングを創り出したり、維持することが求められる職種ですが、より大きな枠組みで捉えると、全社的な取り組みに拡張していくことができます。例えば、スローガンの作成や、CI(コーポレートアイデンティティ)の刷新やガイドラインの策定などにも関わることができます。これは、企業活動の上流工程に踏み込むことで、社内的な立ち位置を向上させるきっかけを作ることにもなります。
デザインの実力アップ
社内にインハウスデザイナーがほとんどいない場合、デザイン的な能力の頭打ちを感じて悩むこともあります。一般的にインハウスデザイナーの仕事や作品はダサいと言われることもあるようですが、工夫次第ではそういった壁を打破することができます。
副業のすすめ
インハウスデザイナーを続けていると、自社のテイストに偏ったデザインや、作りやすいデザインになりがちで、新たな切り口や、一皮むけたデザインに挑戦する機会がなかなかありません。
会社によっては禁止されているケースもありますが、副業ができるのであれば、ぜひ社外のクリエイティブを作る機会を自分に与えてください。外注先という立場になって他社のデザインを受託すると、より緊張感をもってデザイン業務に取り組むことができますし、否応なく自分の実力を目の当たりにすることになりますので、自然と努力したり、勉強したいという気持ちになりやすいです。

また、依頼先からのフィードバックを受けることで、他社はどういった点に注意してデザインを作り上げているのかを知ることもできますし、自分のデザイン力の市場価値を理解するヒントにもなりそうです。
副業をするならば、ランサーズやクラウドワークス、ココナラなどのサービスでデザイン業務を受託するのがおすすめです。
最新情報をキャッチしよう
ピナトンが長年インハウスデザイナーをしていて体感しているのが、デザインソフトの進化です。(ピナトンは、Adobeイラストレーターのバージョンがまだ7だった頃の時代からデザインをしています)
どうしても、使い慣れた機能を駆使してしまいがちですが、一度使用ソフトの公式サイトへ行って、最新機能を流し読みし、日常の作業で活用できそうなものがあれば、ぜひチュートリアル動画を視聴してみてください。

一昔前は苦労していた、人の髪や動物の毛を背景から切り抜くのも、今では一瞬で行えるようになりました。
積みあがったタスクに埋もれて、ついつい勉強時間の確保がおざなりになりがちですが、意識的に最新情報をキャッチすることで、確実に業務は効率化しますし、精度もアップしていきます。従来自分の知り得る限りの機能では創り出すことができなかったデザインも、手早く実現できるかもしれません。インプットが良質なアウトプットを生み出します。
ターゲットへの理解を深めよう
「誰のためのデザインであるのか」は、よく意識される着眼点ですが、インハウスデザイナーがプロモーション素材を作成する場、デザインのターゲットはお客様や潜在顧客となります。実際に、自分達が作るデザインを見て「買う」「買わない」「好き」「嫌い」「気になる」などの感情を示してくれる相手のことですね。
インハウスデザイナーは営業の現場へ出向く機会が少ないかもしれませんが、どういった立場の方がターゲットになっているのか、どういった困りごとを抱えて生活や仕事をしているのかを熟知しておくことは重要です。
BtoBは理論、BtoBは感情で購買の可否が決定されがちと言われていますが、どういったケースでも、ターゲットの心に寄り添って共感したり、問題提起するデザインは、人を動かす原動力になります。
ピナトンの場合は、実際のお客様へインタビューしたり、営業担当者へヒアリングすることで、自社製品・サービスのペルソナ像を確立していました。ターゲットの解像度が高くなってくると、自ずとデザインの方向性の判断もしやすくなってきます。
デザインの価値を社内へ知らしめたい方へ
デザインは誰しもができることではないにも関わらず、得てして価値を低く見積もられがちです。なぜなら、デザインの最終形態からは、そのデザインに至った試行錯誤や背景調査、制作の工数などが見えづらく、物理的な「もの」でないことも多いためです。特にデジタルで表現されるデザイン(Webサイトや広告、イラストなど)は複製も簡単なので、なぜか軽んじられてデザイナーの苦労や思い入れが完全に見落とされてしまうこともあります。
しかし、身の回りに目を向けると、ありとあらゆるものが「デザイン」されていて、便利さや安全、心配りといった方面から、私達の生活を豊かにしてくれています。ですが、それに気付く人はほんの一握りなのが実情です。
では、どうやってデザインの価値を表現すれば良いのでしょうか。答えは、デザインの効果を数字で見える化することです。

オフラインの媒体は効果測定が難しいのですが、オンラインの媒体であれば、比較的に簡単、かつ無料で数値化することが可能です。
Webサイト
サイトの滞在時間や、直帰率、コンバージョン率、ヒートマップを見ることで、サイトが想定通りにうまく機能しているかどうか判別したり、サイトがどれだけ売上や認知度向上などに貢献しているか計測することができます。
広告やバナー
デザインの候補が複数ある場合は、ABテストを実施して、どういったデザインが多くクリックされ、コンバージョンさせられるのか、検証することができます。
メルマガ
どのようなデザインや構成、コピー、コンテンツを掲載することで開封率やクリック率が高まるのか、検証することができます。
デザインの良さを数値化するためには、デザインの知識の他、マーケティングの知識やデータの分析力も必要になります。ピナトンの場合は、勉強のためにオンラインサロンへ参加したり、オンラインセミナーを受講することで情報収集しています。
まとめ
ここまで、ピナトンの経験に基づいたインハウスデザイナーの紹介でした。インハウスデザイナーは孤独なことも多いため、本人のモチベーションを維持させたり、自主的な勉強が必要だったり、業務範囲が広かったりと大変なことも多いです。そういった自由度の高さがある分、裁量範囲が広いことで、やりがいを強く感じられる職種でもあります。自社のために自社のためのデザインをコツコツと創り上げていくインハウスデザイナーは、自社に特化した愛社精神溢れる行き届いた仕事ができることも特徴。こんな職種についてみたいという方は、ぜひチャレンジしていただきたいです。
ピナトンは、インハウスデザイナーとして経験を積んだ後、フリーランスとして独立しました。その経緯についてはこちらをご覧ください。